次男に乳アレルギーがあると分かったとき、私は不安で「どうすればいいのだろう」と悩みました。
この記事は私たち家族の体験談です。子どものアレルギーは、誰のせいでもありません。困ったときは一人で抱え込まず、必ず医師や周りに相談してほしい──そんな思いを込めて書きました。
気づいたきっかけ
最初に異変を感じたのは、妻が次男にミルク粥を食べさせたとき。体にじんましんが出たのです。
小児科で検査を受けると「乳製品」「卵白」などにアレルギーがあることが分かりました。
特に乳製品の数値は高く、私は「乳製品は一切食べさせてはいけない」と思い込んでしまいました。
翌年も、その次の年も数値は下がらず、不安が続きました。
食物経口負荷試験(OFC)との出会い
次男が「自分は乳製品や卵を食べられない」と理解できるようになった頃、妻から「負荷試験をやってみよう」と提案がありました。
食物経口負荷試験(OFC)とは
少量から原因食物を段階的に摂り、反応の有無を確認する検査です。
必要に応じて入院や点滴など、安全体制を整えた上で行われます。
(参照:foodallergy.jp)
5歳のとき、負荷試験を実施できる病院に相談しました。
しかし、次男は今まで食べた事が全く無かったので、効果が薄いと言われました。
そのため、自宅で少量から乳製品を食べさせることを提案されました。
医師からは次のような説明を受けました。
- どれくらいで症状が出るかを確認することが大事
- 手で顔を触った場合に出る反応は気にしなくてよい
- 実際に食べた量を記録すること
- 今のうちに食べさせないと、今後ますます食べられなくなる
私たちは家庭で少量ずつ食べさせる挑戦を始めました。
日常の工夫(「全く食べさせない」にしないために)
私たちが実践した方法は
- 豆乳グルトにヨーグルトを1g混ぜる
- はちみつやジャムを加えて食べやすくする
- 食べた後に症状が出た場合だけ記録する
- 毎日1gずつ増やし、10gを超えたら5g単位で増量
- 好きな食べ物と一緒に食べさせる
- 保育園には常にアレルギー用の薬を預ける
医師との目標は「とりあえず100g!」。
幸い、口に入れて重い症状が出ることはありませんでした。
50gからの壁と、ご褒美の力
しかし、50gを超えたあたりから進まなくなりました。
ヨーグルトの量が増え、味を変えても食べません。料理に混ぜても直ぐに気づいて拒否。嗅覚が鋭くなったのかもしれません。
それでも毎日つきっきりで食べさせました。
最後に効いたのは「ご褒美」。そのおかげで100gを完食!
年長の終わり頃から、給食もみんなと一緒に食べられるようになりました。
「みんなと一緒に食べられて嬉しい」と笑顔で話してくれた姿は、今も忘れられません。
最後に
次男は「食べるな」と言われて育ち、途中から「食べなさい」と言われました。混乱したと思いますが、必死に向き合ってくれました。
アレルギーがあっても、誰も悪くありません。
ただ、相談すること・学ぶことは誰にでもできます。
私たちの場合は少しずつ乳製品を食べられるようになりましたが、食べることで命に関わる場合もあります。必ず医師と相談しながら進めてください。
正しく理解し、周囲と協力すれば、生活はきっと整っていきます。
この体験談が、同じように悩む方の小さな安心につながれば嬉しいです。
そして、次男のアレルギーを通して、私たちは本当に多くの人に助けてもらいました。今も小学校で先生方に支えていただいています。
誰かに助けてもらうことは決して恥ずかしことではありませんが、先生方をはじめ、周りの方々にとても感謝しています。


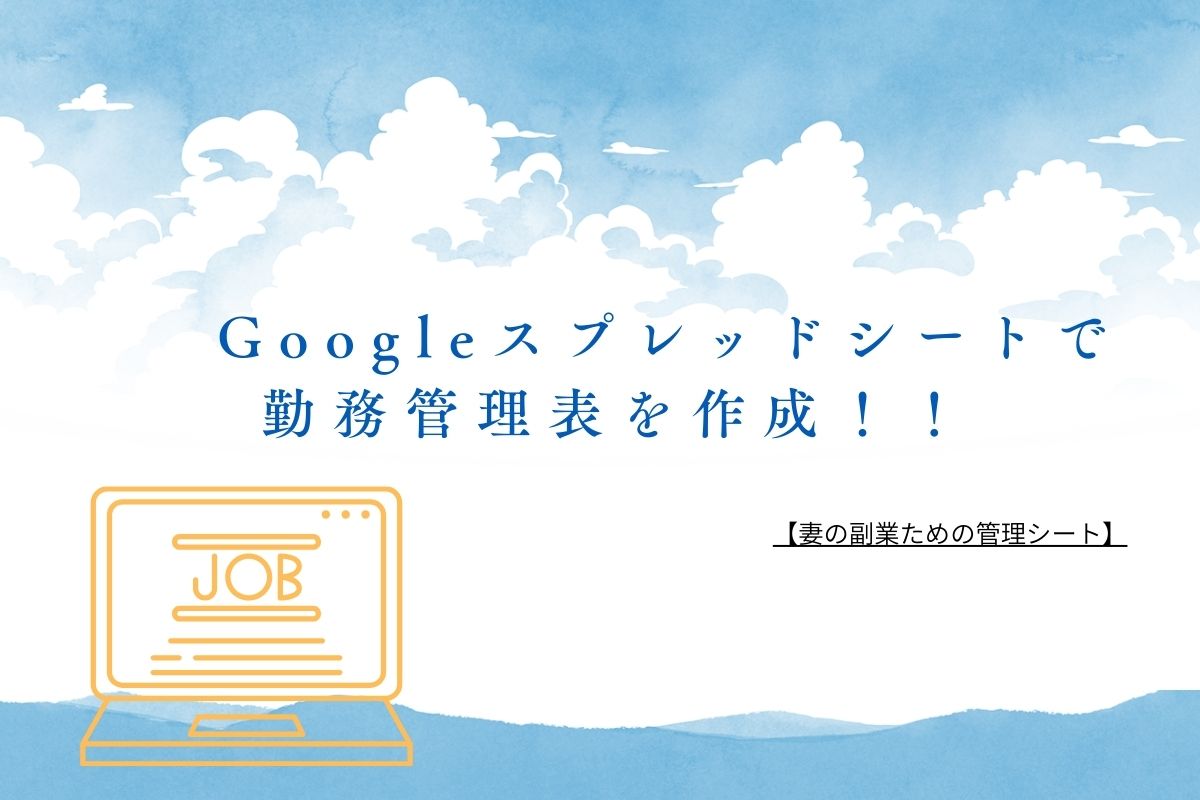
コメント